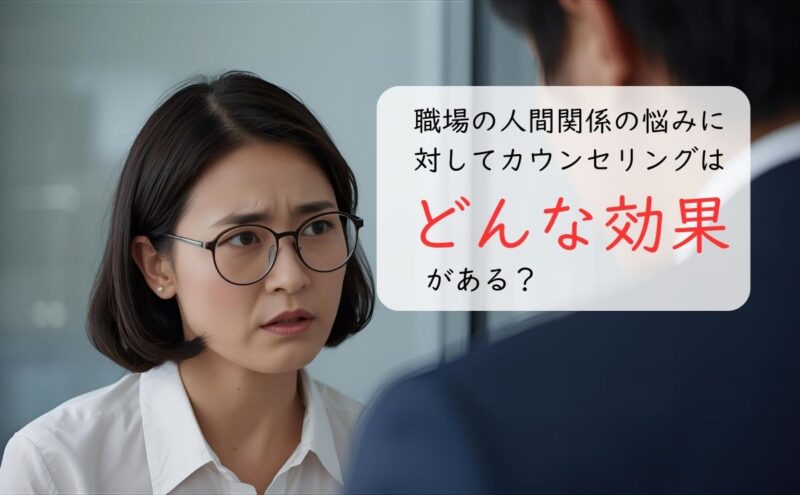感情のコントロールが上手くなる
人間関係の悩みに対して心理カウンセリングを受けると、多くの方がまず実感されるのが「感情コントロールが上手になる」という変化です。
私たちは、人との関わりの中で怒り・不安・悲しみ・嫉妬など、さまざまな感情を抱きます。
ところが、その感情が高ぶったまま相手にぶつけてしまうと、望まない衝突を招いたり、逆に我慢しすぎて自分を傷つけてしまうこともあります。
カウンセリングでは、感情を無理に抑え込むのではなく、まずは安心できる場で気持ちを言語化し、感情の背景やパターンを理解することから始めます。
そして呼吸法や認知の切り替え(リフレーミング)などを使って気持ちを落ち着かせる練習を重ねることで、感情に振り回されるのではなく、自分で感情を扱えるようになっていきます。こうした力は、人間関係のトラブルを未然に防ぎ、円滑な対話を支える大切な土台になります。
事例:上司の言動にすぐイライラしてしまうAさん(30代・女性)

Aさんは職場で、上司のちょっとした指摘や口調に強くイライラしてしまい、その場で反論したくなったり、後で思い出して怒りがぶり返して眠れなくなることに悩んでいました。感情を抑えようとしても我慢できず、逆に同僚にきつい言い方をしてしまうこともあり、「人間関係がどんどん悪くなっている」と感じていました。
カウンセリングではまず、怒りが爆発する前に身体に出るサイン(肩のこわばり・呼吸が浅くなる・手が冷たくなる等)に気づく練習を行いました。そのうえで、イライラを感じたときはその場で「深呼吸して10秒黙る」「一旦席を外してコーヒーをいれる」といった“クールダウン行動”を試すよう提案しました。さらに、上司の言葉を「人格攻撃」ではなく「仕事上の確認」と捉え直すリフレーミングも練習しました。
数週間後、Aさんは「前ほどカッとなることが減って、冷静に話を聞けるようになった」と話してくれました。怒りに振り回されずに対応できるようになったことで、職場の雰囲気も以前より穏やかになっていきました。
認知の歪みに気づける
人間関係で悩みが続いているとき、多くの場合その背景には「認知の歪み」が隠れています。認知の歪みとは、物事を極端に解釈したり、偏った見方をしてしまう思考のクセのことです。たとえば「上司が挨拶を返してくれなかった=嫌われているに違いない」と決めつけてしまうのも、その一例です。
心理カウンセリングでは、こうした自動的な思考パターンを丁寧に言語化しながら、「他の解釈の可能性はないだろうか?」と一緒に検討していきます。視点を増やす練習を重ねることで、「嫌われた」と即断していた場面を「忙しくて気づかなかったのかも」と柔軟に捉え直せるようになっていきます。認知の歪みに気づき修正できるようになると、対人関係における過剰な不安や誤解が減り、より落ち着いた気持ちで人と関われるようになるのです。
事例:同僚の態度を「自分への嫌悪」と受け取っていたBさん(40代・男性)

Bさんは職場で、同僚が自分にだけ冷たい態度をとっていると感じ、「きっと嫌われている」「陰で悪口を言われているに違いない」と思い込み、人との関わりを避けるようになっていました。仕事中も常に緊張していて、会話をするときは相手の表情ばかりを気にしてしまい、業務にも集中できなくなっていました。
カウンセリングではまず、こうした思考の背景にある「認知の歪み(読心・決めつけ)」に気づくため、出来事・思考・感情・行動を記録する“思考記録表”をつけてもらいました。そして、「本当にそうだと確証できる証拠はあるか」「他の可能性は考えられないか」を一緒に検討していきました。するとBさんは、「実際はその同僚は皆にそっけない口調だった」「自分の不安が“嫌われた”という解釈を生んでいた」と気づきました。
数週間後には、「相手の態度=自分への否定」と決めつけることが減り、「今日は疲れているのかも」と落ち着いて受け止められるようになりました。その結果、自分からも自然に話しかけられるようになり、職場の人間関係も少しずつ和らいでいきました。
境界線(バウンダリー)が引ける
人間関係で悩みが絶えない人の多くは、「境界線(バウンダリー)」があいまいになっていることがあります。境界線とは、自分と相手との間にある“ここから先は自分の責任・ここから先は相手の責任”という心の線引きのことです。
境界線がうまく引けないと、相手の機嫌を常に気にして疲れたり、頼まれごとを断れずに抱え込み、無理をしてしまいます。
心理カウンセリングでは、まず「自分が本当はどう感じ、何を大切にしたいのか」を丁寧に整理し、そのうえで「断る」「助けを求める」「距離をとる」といった具体的な対人スキルを練習していきます。少しずつ境界線が引けるようになると、相手に振り回されずに穏やかな関係を保ちながら、自分自身を大切にできるようになっていきます。
事例:頼まれると断れずに疲れきっていたCさん(30代・女性)

Cさんは職場で、同僚からの頼まれごとをいつも引き受けてしまい、自分の仕事が後回しになって残業続きでした。断ると嫌われるのではないかと不安で、無理をしてでも応じてしまううちに疲れが限界に達し、「もう人と関わるのがつらい」と感じてカウンセリングを受けることになりました。
カウンセリングではまず、「相手の期待に応える=良い人でなければならない」という思い込みに気づき、それが自分の限界を無視する行動につながっていたことを一緒に整理しました。そして、「今は手がいっぱいなのでお手伝いできません」「午後なら30分だけ対応できます」といった“やんわり断る”練習をロールプレイで繰り返しました。また、頼まれごとを受ける前に一呼吸おいて「今の自分にできるか」を考える習慣もつけました。
数週間後、Cさんは「以前より自分の都合を大切にできるようになった」と話し、周囲との関係も大きく崩れることなく、気持ちに余裕を持って過ごせるようになりました。
安全な対話の型が身につく
人間関係の悩みが続く背景には、「どう伝えたらいいか分からない」「話すといつも衝突してしまう」といったコミュニケーションのつまずきが隠れていることがあります。
心理カウンセリングでは、こうした対話のストレスを減らすために、「安全な対話の型(コミュニケーションスキル)」を学び、練習していきます。たとえば、相手を責めずに自分の気持ちと要望を伝える「I(アイ)メッセージ」や、意見が対立したときに合意を目指す「DESC法」などがその代表です。
これらは、感情的にならずに冷静に話し合うための“会話の手順”のようなものです。安全な対話の型が身につくと、言いたいことを我慢せずに伝えられるようになり、衝突や誤解が減って、お互いに尊重し合える関係を築きやすくなります。
事例:同僚と意見が対立すると感情的になってしまうDさん(20代・男性)

Dさんは、職場で同僚と意見がぶつかるとすぐ感情的になってしまい、「いつも怒っている人」と周囲に思われてしまうことに悩んでいました。本当は冷静に話し合いたいのに、相手の言葉にカッとなって声が荒くなり、その後自己嫌悪に陥るという悪循環を繰り返していました。
カウンセリングではまず、「感情が高ぶると話し合いがうまくいかない」ことを理解し、話す前に一呼吸おく練習を始めました。そのうえで、自分の気持ちと要望を冷静に伝えるために「I(アイ)メッセージ」や「DESC法」の型を使ったロールプレイを繰り返しました。たとえば、「あなたが遅れたから困った」ではなく、「会議が予定より遅れて進行が不安になった。次回は時間通りに始めたい」と伝えるように練習しました。
数週間後、Dさんは「感情的にならずに意見を言えるようになった」と話し、以前よりも建設的な話し合いができるようになったことで、同僚からの信頼も回復していきました。
まとめ
人間関係の悩みは、多くの人が人生の中で何度も直面するものです。
心理カウンセリングでは、ただ話を聞いてもらうだけではなく、「感情をコントロールする力」「認知の歪みに気づく力」「境界線(バウンダリー)を引く力」「安全な対話の型を身につける力」といった、人間関係をより良くするための具体的なスキルや視点を身につけることができます。
こうした力が少しずつ育っていくことで、人に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら穏やかな関係を築けるようになります。人間関係で悩みが続いているときこそ、一人で抱え込まずに専門家と一緒に心を整えていくことが、回復と成長への大切な第一歩となりますよ。