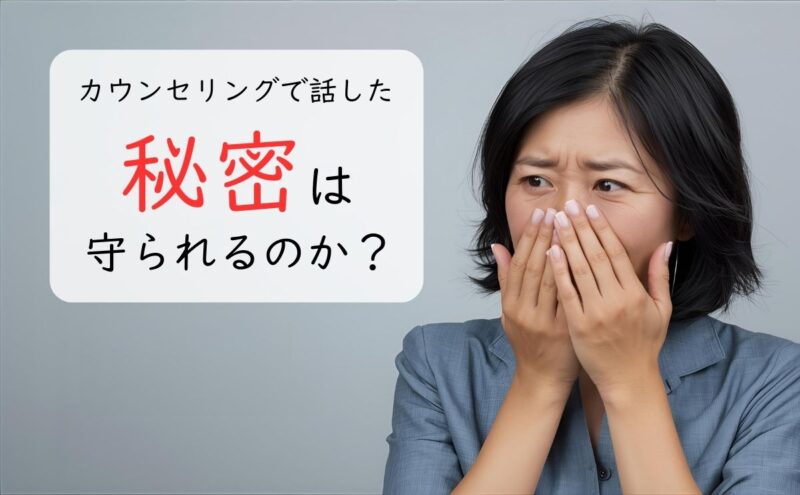カウンセリングを受けてみたいと思っても、最初の一歩を踏み出すときに多くの方が不安に感じることがあります。
その代表的なものが、「カウンセリングで話したことは本当に秘密にされるのだろうか?」という疑問です。
とても大切なことですし、自然な不安でもあります。
この記事では、カウンセラーとしての守秘義務と例外について説明していきます。
秘密が漏れないか心配するのは当然のこと

初めてカウンセリングを受けるとき、多くの人は「誰にも言えないことだからこそ相談したい」という思いを抱えています。
中には、家族や友人にすら打ち明けられなかった悩み、過去の辛い体験、あるいは職場や人間関係での深刻な問題など、デリケートな話題も含まれているでしょう。
そうした大切な話をするのですから、「カウンセリングで話したことは本当に秘密にされるのだろうか?」と心配するのは当然です。
実際に私はクライエント様から、
「話したい内容の中に、田中先生の前職と同じ人がいるのですが、カウンセリングの内容が漏れることはないですよね?」
「話したい内容の中に、田中先生が卒業した大学学部と同じ人がいるのですが、秘密は守ってもらえますか?」
等と確認されることがあります。
クライエント様の秘密漏洩に対するご心配を強く感じる瞬間です。
カウンセラーには守秘義務があります

心理カウンセラーには、相談者から聞いた話を第三者に漏らさない「守秘義務」があります。
これは単なるモラルではなく、法律や倫理規定として定められているのです。
公認心理師や臨床心理士、産業カウンセラーといった国家資格や歴史ある知名度の高い資格団体に所属するカウンセラーは、特に厳格な守秘義務を負っています。
その守秘義務や倫理規定を紹介します。
まずは公認心理師の守秘義務を定めた公認心理師法です。
(秘密保持義務)
引用元:厚生労働省・公認心理師法(平成27年09月16日法律第68号)
第四十一条 公認心理師は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。公認心理師でなくなった後においても、同様とする。
次は臨床心理士が所属する日本臨床心理士会の倫理綱領を紹介します。
第2条 秘密保持
引用元:一般社団法人日本臨床心理士会倫理綱領
会員は,会員と対象者との関係は,援助を行う職業的専門家と援助を求める来談者とい
う社会的契約に基づくものであることを自覚し,その関係維持のために以下のことについ
て留意しなければならない。
1 秘密保持
業務上知り得た対象者及び関係者の個人情報及び相談内容については,その内容が自他
に危害を加える恐れがある場合又は法による定めがある場合を除き,守秘義務を第一とす
ること。
産業カウンセラーが所属する日本産業カウンセラー協会の倫理綱領を紹介します。
信頼関係の確立
引用元:日本産業カウンセラー協会 倫理綱領
第6条 産業カウンセラーは、クライエントとの信頼関係を積極的に形成する。
2 産業カウンセラーは、個人と組織の秘密に関する守秘義務については、特に個人のプライバシー権を尊重する。
3 産業カウンセラーは、クライエントおよび他の専門職、企業・団体などの関係者との信頼関係確立のため、職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。
心理カウンセラーは以上のような守秘義務を肝に銘じて活動してるので、秘密が漏れることはありません。ご安心ください。
どうしても秘密漏洩が心配な人は、そのカウンセラーの資格を認定した団体の倫理綱領などを調べて守秘義務について明記してあるか調べてみるのもよいかもしれません。
守秘義務にも例外はある
ただし、守秘義務にはいくつかの例外があります。これは相談者や周囲の人の命や安全を守るために必要な場合です。具体的には次のようなケースです。
- 自殺の危険が切迫しているとき
- 他者に危害を加える可能性が高いとき
- 児童虐待や高齢者虐待など、法的に通報義務がある場合
- 裁判所から記録提出を求められるなど、法的手続きによって要請された場合
以上の場合には、関係機関と協力します。
守秘義務の例外:自殺すると連絡があった事例
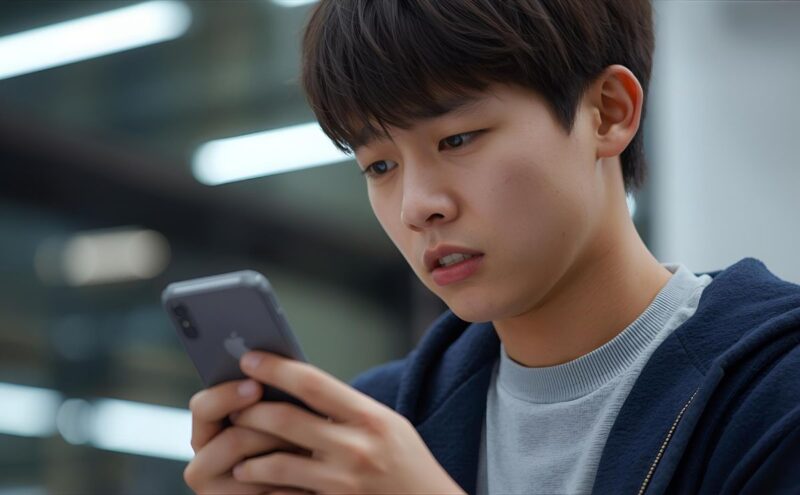
ある日、ホームページのお問合せフォームから、自分の状況と「自殺する」と書かれたメールが届きました。送り主は匿名でしたが、「東北地方のある高等専門学校の生徒」と名乗り、メールアドレスは記載されていました。
私は守秘義務の例外であり、一刻を争うと判断し、その日の午前中にその学校へ通報しました。ほどなく教頭先生から折り返し連絡があり、「該当の生徒を特定する方向で動きます」とのこと。その生徒が無事であることを祈りつつ経過を待ちました。
夕方、再び教頭先生から連絡が入り、「生徒は特定できましたが、実際には本校の生徒ではありませんでした」と報告を受けました。いたずらだったのかは分かりませんが、真剣に対応してくれたことに感謝の言葉をいただき、通報してよかったと強く思ったことでした。
守秘義務の例外:警察に協力した事例

以前、ある犯罪事件の被害者となった女性に対して心理カウンセリングと、被害のトラウマ解消のための心理療法を行っていたことがありました。
ある日、その事件を担当する捜査員から電話があり、「カウンセリングの記録を提供してほしい」と依頼を受けました。その数日後に、「捜査関係事項照会書」が郵送されてきました。警察署長の名義で刑事訴訟法第197条2項を根拠にしてカウンセリングの記録の情報開示が求められていました。
私は法律に基づく正式な要請であることを確認し、依頼通りにカウンセリング記録をその捜査員宛に郵送しました。
普段は秘密を守ることが基本のカウンセリングですが、法的手続きの中では例外的に記録を提供する場面もあるのだと実感した出来事でした。
安心して一歩を踏み出して

カウンセリングは「安全な場」であることが何より大切です。
もし今あなたが「話したいけど、秘密は守られるのだろうか」と不安を抱いているなら、その気持ちはとても自然で大切にすべき感覚です。
そして同時に、カウンセリングの世界では守秘義務が基本であり、安心して話していただける仕組みが整っていることを知ってください。
守秘義務の例外についてもご説明しましたが、そのような例外の事例は私の18年間のカウンセリング経験の中でわずかに数件だけです。滅多にないことですからご安心ください。
あなたが信頼できるカウンセラーを見つけられれば、「ここでは安心して話せる」と感じられるようになり、そこから心の回復や成長が始まっていきます。
まとめ
- カウンセリングには守秘義務があるため、話した内容は基本的に外に漏れません。相談者との信頼関係を第一に、守秘義務を守る姿勢が徹底されています。
- 例外として、自殺や他者への危害、法的要請、虐待など命や安全に関わる場合には、必要最小限の情報が関係機関と共有されることがあります。
- 「秘密が守られる」と知ることで安心して話せるようになり、カウンセリングが効果を発揮します。